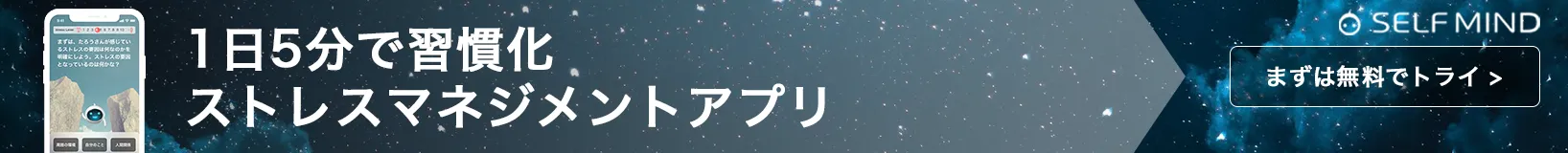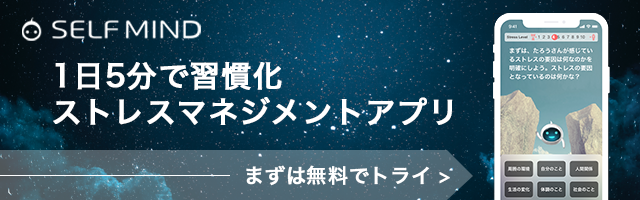- 「仕事で失敗した」
- 「傷つくことを言われた」
- 「階段で転んだ」
辛いことや不安なことがあったとき、誰かにそれを話したくなったりしませんか?
実は、このような心理については科学的にも研究が進められており、ネガティブなことを誰かに話したいという心理には主に「認知的側面」と「対人的側面」があると考えられています。
辛いことや不安なことがあった時、誰かに話したいと思うにはちゃんと理由があるのです。
目次
メンタルを保つカタルシス効果

ある研究で、不快な気持ちになるような映像を見たとき、人はその体験を他者に共有するかどうかについて調べたという実験があります。
映像を見た被験者を友人と待合室で二人きりにした結果、全被験者の95.3%の人が友人にその映像について語ったことがわかっています。また、他者に話すことを禁止した場合でも、一週間後には53%の人がそのことについて他者に話したという報告もあります。
人は、禁止されても止めることができないほど、嫌なことがあった時にそれを他者と共有したいという欲求が強い生き物なのです。
臨床心理学においては、生じた情動を言語化することには、不安や緊張を取り除くカタルシス効果があり、精神的な健康につながるとされています。言葉にして誰かに伝えるということは、抑うつからの回復が期待される行動であり、人は「認知的側面」と「対人的側面」からその効果を得ているのです。
誰かと話したいという2つの心理とは
心理1.概念の揺らぎを正し、不安を解消する「認知的側面」
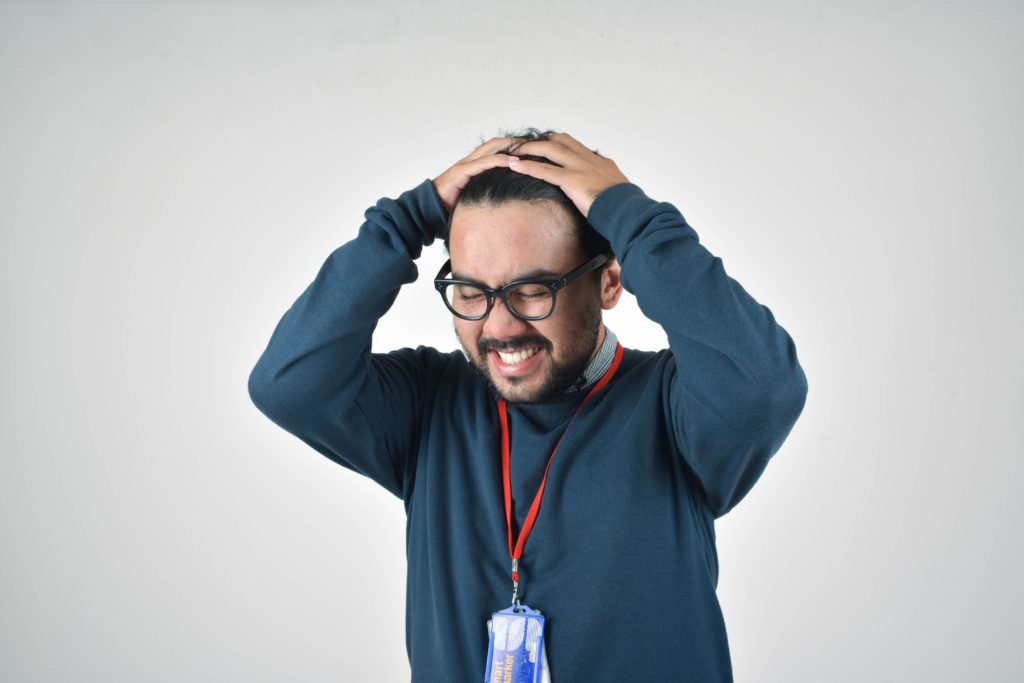
つらいことがあった時はモヤモヤしたり不安になったりするものです。不安になるというのは、言い換えれば自分自身や周囲に対して「信頼できない」「認識できていない」というような概念の揺らぎが生じている状態と言えます。
- ・何が起きたのか整理したい
- ・どうしてこうなったかを明らかにしたい
- ・どんな社会的サポートが得られるかを知りたい
認知的側面においては、こういった心理が他者へ感情を吐露する理由だと考えられています。 気の置けない仲間や家族、または専門家と話し合い、自身の中で定義されている信頼を回復させる必要があるのです。
心理2.自分を知ってほしいという「対人的側面」

また、つらいことがあった時、人はどうしても自分に対して意識を向ける傾向にあり、周りに目を向けられなくなりがちです。
つらいことで感じるさびしい気持ちや不安な気持ちから逃れるため、人は嫌な経験について誰かに共有し、ネガティブ感情を発散させようとします。「自分の状態を知ってもらいたい」「受け入れてほしい」などの強い気持ちを他者に表明し、コミュニケーションを求めるのです。
対人的側面においては、このような承認欲求的な心理が話したくなる理由とされています。
恥ずかしい経験はすぐに話したくなる?

- 「スピーチをして噛んだ」
- 「繁華街を歩いていて転んだ」
- 「友人かと思って声をかけたら別人だった」
日常生活において、時として恥ずかしいと思うような経験をすることもあるでしょう。
ある大学で、「最も悲しかった出来事」「最も怒った出来事」「最も恥ずかしかった出来事」について、他者にそのことを話したか、またそのタイミングはいつだったかについての調査が行われました。
恥ずかしいことは他の人に話したくないものかと思いきや、参加者たちは71.4%の割合で他者とその経験を共有していました。さらにそれらは、約半数の割合で、出来事の直後に共有されていたのです。
これは、恥ずかしい出来事について誰かから攻撃されないように先手を打っていると考えられます。恥ずかしいという気持ちが芽生えた時点で、人は少なからず心に傷を負っています。その傷口は、他人に笑われたり責められたりすることでみるみる大きくなり、修復が難しくなることでトラウマ体験となり、後の人生に暗い影を落とすことになりかねません。
そうならないように、あえて自分から先に口にすることで心の防衛線を張り、それ以上傷を広げないように自分を守っているのです。
これは日本人だけでなく欧米人にも見られる現象で、ベルギー、スリナムなど6箇所で行われた感情の社会的共有行動に関する調査では、恥ずかしいことを言葉にする人の割合は国や年齢差、性別による差は認められませんでした。恥ずかしいことがあったときに誰かに話したいと思うのは古今東西、老若男女共通の現象のようです。
人と話したくないと思うときもある

もちろん、恥ずかしいことやネガティブなことを話したくないと思うこともあるでしょう。
理由は大きく分けて2つ考えられますが、どちらにも共通して言えるのは、両者とも自己防衛の側面が強いということです。
理由1.人に弱みを見せたくない
一つは、人に弱みを見せたくないという心理です。
これらの人の多くは「弱みを見せたら立場が弱くなる」「ヒエラルキーが下がる」といったような対人関係における立場を気にしています。特に、社会生活を送る中ではこういった立場やポジションは重要で、プライドを保っているのです。
また、人に弱みを話すことで否定されたり、嫌われるのではないかという不安を抱くケースもあります。
この場合は自己肯定感が低いことで自信が持てず、傷つきたくないという心理が働いていることが考えられます。何かアドバイスが欲しいわけではなく、「こう思っている」という思いをただ聞いてもらうだけの相手がいるといいかもしれません。
理由2.改めて認識したくない
もう一つは、自分の弱みを改めて認識したくないという心理です。
ネガティブなことや恥ずかしいことを体験したあとに、それをもう一度誰かに話すことでネガティブ体験を呼び起さなくてはなりません。そうなると自分の弱い部分を再認識させられるので、傷口に塩を塗る行為にもなり得ます。
これはプライドの高い人に多く見られるケースで、弱みを実感することで他人より劣っていると感じたり、自分はダメな存在なんだと自己否定に陥るのです。周囲の目を意識する傾向が強く、自意識が高いことが考えられるので、肩の力を抜いて自然体でいることを心がけるといいでしょう。
相手への思いやりを持とう!

一方、ネガティブな経験を話された相手にとっても、話の内容や回数によっては多かれ少なかれストレスがかかってしまうことがあります。
話を聞いてもらいたいという場合、つい自分本位になり聞いてくれる相手の気持ちを無視してしまいがちです。善意で聞いてくれる相手に対して感謝を忘れずに、思いやりを持って接することが大事です。
また、今はスマホアプリでメンタルヘルスをケアできる時代です。AIロボと会話しながら心を落ち着かせ、感情を記録することで自身を客観的に見ることができます。ぜひ一度「AIカウンセリング」を試してみてください。
→ SELF MIND
何かあったとき、その体験を人に共有するのはごく自然なことと言えます。
自分の中だけで解決できる問題ならまだしも、ネガティブ体験によって心が傷ついてしまうことを防ぐためにも、誰かに話して自己防衛することは大切なのではないでしょうか。
Source:
川瀬 隆千
「感情を語る理由:人はなぜネガティブな感情を他者に語るのか」(宮崎公立大学人文学部紀要 2000-03-21)